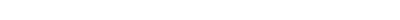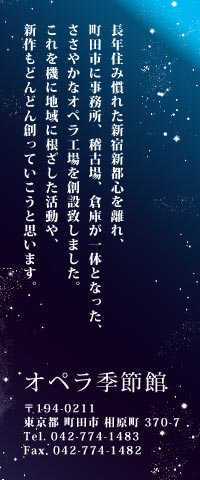ブログ
-
2014.3.31
「ミュージカリスト」という職業を設定します。
2014 3月 伊勢谷宣仁
これは私が2013年春に勝手に創りだした造語で、英語標記すると<Musicalist>となりますが英語の辞書にはもちろんありません。定義づけすると、ミュージカルに不可欠な歌唱力、舞踊力、演技力の3要素を有し、かつ舞台芸術全般の教養・素養を身につけた人、ということになります。
今、日本では劇団四季が本格的なミュージカル産業を構築したこともあって、沢山のミュージカル公演が行われています。一頃に比べると全体に専門性も高くなってきているようです。そんなわけで専らミュージカルの舞台に出演し生計の基本を立てている人たちが多くなってきています。 一方ミュージカル公演では、売らんがために著名でちょいと器用ならミュージカルの舞台に立たせる現状も少なくありません。出演者の出自が歌手であったり、根っからテレビタレントだったり、噺家だったりする場合もあります。要するにミュージカルはオペラ歌手とは異なり、役や製作の狙いによっては誰でも出演可能なものとなっています。 では、専らミュージカルに出演し生計を成している人を何と呼ぶか? 最近<ミュージカル俳優>という言葉を使用している人が増えている。
<ミュージカル俳優>、英語圏では<Musical Actor>、ミュージカル女優なら<Musical Actress>と標記している。(本来musicalはmusicの形容詞だったと思いますが、今では名詞化している)
宝塚出身者が東宝製作等のミュージカルにかなり出演していますが、多くは<女優>としているようです。もっとも<元宝塚>という冠がほぼ間違いなくついてきますが・・・。
さてどうも、しっくりしません。
今、私は昭和音楽大学のミュージカル・コースの責任者としてその任に当たっていますが、学生が大学4年間で学ぶことはミュージカルに関わるほとんど全てのことに及んでいます。4年で充分なはずはありませんが・・。 私は、私たちの希望するミュージカル全般の素養を身につけて卒業した彼、彼女らなら、「ミュージカリスト」として堂々と名刺に刻印してもらっていいと思います。ミュージカルの舞台に立とうが、指導者になろうがそれはかまわないと思っています。ただ、それを名のるに相応しい誇りと技量をもって欲しいと思っていますが。もちろん他の人が、舞台芸術界で<Musicalist>を名のりたいならそれもいいと思います。この造語もやがて名詞化するでしょう。
ミュージカリストという職業を設定します
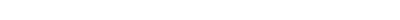
-
2013.6.12
夕焼け 小焼けで 日が暮れて
山のお寺の 鐘がなる
おててつないで みなかえろう
からすと いっしょに かえりましょ
子供が かえったあとからは
まるい大きな お月さま
小鳥が夢を 見るころは
空には きらきら 金の星
この詩の作者は中村雨紅(1897〜1972)。詩に曲をつけ一躍有名なものとしたのは長野県出身の作曲家、草川信(1893〜1948)。
一定の年齢の方なら誰でも知っているこの詩の舞台となったのは、雨紅の出身地八王子市恩方町とされている。JR八王子駅では
この歌メロを電車の発車に使用しているし、同市のふれあいの里には雨紅の資料館もあってそれが定説とされている。
しかし・・・
この詩の創作の舞台となったのは「町田市の相原町」という説が打ち出されている。
同町のまちづくり協議会理事、守屋松則氏等は・・・
◆「〜子どもが帰った後からは 円い大きなお月様〜という一節について、恩方では午後八時にならないと満月が見えない。子どもが
帰る時間と符号しない。また、相原から恩方に帰るカラスはいても、恩方からさらに山奥に帰るカラスはいないはずだ」。
◆雨紅は教師だった1917年当時、叔母の嫁ぎ先である相原の中村武造の養子になり住んでいた。そこで相原を東西に走る町田街道から、
西の高尾山の夕日を眺め詠んだのだろう。
そんな訳で創作の舞台は相原地区ではないかとした。
かくて同地区の諏訪神社に「夕焼け小焼けの」歌碑を建てた(2010)。
つまり恩方は生誕の地、相原は創作の地というわけだ。
相原は著名な詩人・八木重吉の里でもある。
この相原にオペラ季節館が越してきたのは2006年。そして前述の守屋松則氏等と一緒に「相原で第九のある音楽祭」を2013年に開催。
14年も開催の予定で、この際「夕焼け小焼け」もテーマのひとつとしてやりますか!
童謡「夕焼け小焼け」と町田市相原町&オペラ季節館
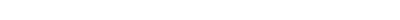
-
2012.2.16
人間国宝で狂言師の野村万作先生とは永年仕事上のお付き合いをさせて戴いているが、そんな狂言公演の最中ふと、不思議に思ったことが・・・。
昨夜は有楽町朝日ホールで万作の会による「法師ヶ母」と「附子」の公演。この内の「附子」こそは狂言作品の最高峰の一つだと僕は思っている。一休さんのとんち噺でも知られるように、なにしろ物語がいい。主人は家を留守にするにあたり、桶の中に附子という猛毒(実は当時貴重な砂糖)が入っているので絶対に近づかないようにと言いおいて家を出る。その嘘から始まって、それを見破る過程の面白さ、そして大事な砂糖を全て食べてしまったことによる後始末の興味、そして最後のこの上もない言い訳の面白さ。それらが軽妙な科白(せりふ)と仕科(しぐさ)、そして狂言特有の擬音効果(酒を飲むとき=ドブドブ・・ドブ、飲み終わると=ピショピショ等)、シオリ(泣く型)、言い訳を終えた後のとぼけた小歌(音楽)等々でつづられ、簡潔でメリハリの利いた極めて高度な演出と相まって完璧といっていい作品に仕上がっている。狂言の醍醐味がここにあり、集大成された一曲といっても過言ではない。
さて、ふと思った。えーっとこれって、一体誰の作品だろう?
狂言は600年も前から、能会の一部として演じられてきた。その能は、例えば著名な「葵の上」の作者は世阿弥。「松風」も「熊野」も「敦盛」も同じ。上演の機会が多い「道成寺」はその父、観阿弥(観世流の開祖)。そして「隅田川」や「石橋」は観世十郎元雅。等々能は多くの曲の作者がわかっている。ところが狂言については、多くの解説本をみても作者は記されていない。不用意というか不見識というか、なんでこんなことが今まで気がつかなかったのだろうと恥じ入る。プログラムを毎回作っていても、作者を入れないのが当たり前になっていて・・・。
能の大成者でもある世阿弥は「前略〜そもそも狂言とは、必ず衆人の笑ひどめくこと、俗なる風体なるべし、笑ひの内に楽しみを含むと云ふ、これは面白くうれしき感心なり〜後略」と記していて一定の関与がうかがわれるが、狂言作者としてはその名を留めていない?。
因に「附子」は、13世紀鎌倉時代の仏教説集「沙石集」の中にその原型があるようだ。また日本各地の民話、朝鮮半島では干し柿に見立てたもの等々、広く東アジアに似たような噺が存在しているという。
附子とは毒性のある植物、トリカブトのこと。野村萬斎師、石田幸雄師がいつにも増して絶妙な「二重奏」で満席の観客を魅了した。
狂言のこと・・・伊勢谷宣仁
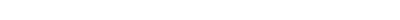
-
2012.2.14
MET(メトロポリタン・オペラ)のオペラで先頃新作初演した「魔法の島」が映画(ライブ版)で公開されている。シェークスピアの二つの戯曲「真夏の夜の夢」と「テンペスト」を下敷きに、バロックの名曲を当てはめるというパスティーシュ(作風の模倣)。
曲はヘンデル、ラモー、ヴィヴァルディ等を使用。物語の場面に応じて選曲、それに歌詞をのせて一つの音楽物語にするというもの。
13日夜、銀座・東劇で観せて戴いたが、一言でいうと「面白かった」。1.に、ソリストがすばらしい。2.に二つの戯曲をうまく換骨奪胎させている。3.に、舞台美術が面白い(コンピューターグラフィックを駆使)。METの多々ある作品の中でこんな「遊び」もあっていいということだろう。メリスマ唱法によるさながらアリア大会の趣きで時には退屈もあったが。「テンペスト」も「真夏・・」もストリーを知らないと全体を理解しにくい。僕は前者をあまり知らないのでちょっととまどったけれど・・・。
ドミンゴが物語の要を担う。声も年齢を感じさせず観客を圧倒。登場するとどーっと拍手が沸く。
企画全体が観客サービスを意識している?。METにおける昨年暮れの「ヘンゼルとグレーテル」(英語上演)も、お菓子の家がミキサーをガーガー廻して菓子作りを体験・食べさせるケーキレストランのようで、実に面白い。どこかの絵本に出てくるようなお決まりの場面じゃ誰も驚かないものねえ。◆パスティーシュなら、僕も2003年にグリムの「ブレーメンの音楽隊」で製作・実演(梅田芸術劇場等で十数回)。中途半端な物語を改訂し、音楽は著名なクラシックの音楽から選曲するなど手法はMETと全く同じ。
オペラ公演は、一般的に原作至上主義が主流だ。でも制作者も指揮者も演出家もある意味では観客代表。オペラを知らない圧倒的人々に成り代わって、つまらない曲だったり、冗漫な物語だったら、どんどん削ったり変えたりする勇気が必要だろう。3月にやってくるピーター・ブルック演出の「魔笛」は、7人のソリストと俳優二人、ピアノ1台という構成。時間も90分。事前に部分を観たかぎり舞台にはほとんどお金がかかっていない。これで世界を回る。
さて、私たち・・硬直した常識や態度から足抜けしよう。様々な可能性を探る事はいつの世でも大切。とは、METからも学んだ。
オペラ「魔法の島」・・・伊勢谷宣仁
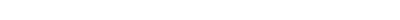
-
2012.1.8
本年も、宜しくお願い申し上げます。
昨年は未曽有の大災害によって、辛く、悲しい出来事の多い年となりました。
その悲しみを乗り越え、今年は「嬉しい」、「楽しい」と言った、多くの幸せなお言葉を聞くことのできる一年になりますよう、オペラ季節館は今後も様々な芸術作品を皆様に提供してまいります。
スタッフ 藤ヶ崎
新年、明けましておめでとうございます。
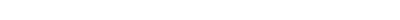
-
2011.12.13
2011年11月20日、どれみ館の初公演が
大好評の末、終了いたしました。一つになった瞬間、
まさにチーム力。
僕は当日、ビデオを回していましたが、
だんだんそのワールドに、
引き込まれていきました。それはまるで、
現代アートを鑑賞しているかのようでした。地域に根をおろし、市民と一緒に
物語を演じる。僕も一スタッフとして、
お手伝いできたことを感謝しつつ
次回公演に向け、全力を尽くして
PRしてまいりたいと思います。スタッフ 藤ヶ崎
どれみ館の初公演を終えて
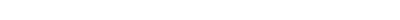
-
2011.11.28
こんにちは、スタッフの藤ヶ崎です。
3日間、芸術季節館を引き払うため、お手伝いをしてきました。
新潟県十日町市松之山にある芸術季節館。
美人林でのコンサートにより、美人林は全国的にも知名度が上がり、コンサートも1400名のお客さんがいらしたと伺ったときは、そのスケールのすごさに僕は驚きました。
また、様々な演者さんが芸を磨いた場所。小学校を改装した建物、そこから、稽古場のような活気と臨場感が今にも伝わってきそうでした。
人とのつながり、多くの人のご助力によって成り立っていた芸術季節館。たたむのは、本当に辛いことと僕も感じています。
けれど、そのスピリッツや当時の空気、感動は、今でも人々の心の中にきっと残されている。その事実を胸に、僕もオペラ季節館にて、多くの人々の心に残るようなコンテンツ作りの、お手伝いを続けていこうと思います!
芸術季節館は人々の心の中に
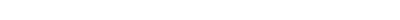
-
2011.11.7
本番まで、残り2週間!
オフィシャルサイトでのお知らせが遅くなりまして、申し訳ありません。
市民によるバラエティ・ミュージカル・ショウ『どれみ館』の初公演が、
来る11/20(日) に迫ってまいりました。この1ヶ月ほどは、通常の土曜14:00~17:00練習を拡大。
土日それぞれ3~4時間ずつ、みっちりと稽古しています。
『どれみ館』の詳しい公演情報を下記にご紹介します。
市民による楽しいバラエティ・ミュージカル・ショウを、ぜひご覧ください。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
うた。踊り。寸劇で!
市民による バラエティ・ミュージカル・ショウ
出演 『どれみ館』
11/20(日) 開場14:00 開演14:30
入場料(全席自由席): 大人1000円 (高校生以上)
子ども500円 (中学生以下)主催:オペラ季節館
町田市相原町370-7お問合せ
Tel: 0120-17-8168
メールフォーム~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、入団者は随時募集中です。
楽譜を読めなくても、経験がまったくなくても、OK。
舞台で歌ってみたい、踊ってみたい、芝居をしてみたい、そんな思いをお持ちの方は、気軽に稽古を見に来てください。また、気軽にお問合せください♪
細野
『どれみ館』11/20(日) 南大沢にて初公演